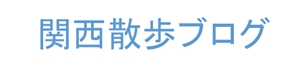グラングリーン大阪(JR大阪駅北側)
大阪府・市は「国際金融都市OSAKA戦略」に基づき「国際金融都市構想」を計画している。
戦略目標
- 2025年度までに30社の金融関連企業(フィンテック含む)・投資家等の誘致
- 2024年度までにユニコーン(企業価値10億ドル以上の非上場企業)3社
- 2024年度までにスタートアップ300社創出
しかし、2024年2月現在、金融関連企業10社、スタートアップ279社が進出しているが非上場の巨大新興企業「ユニコーン」は1社もない。
引用 産経新聞
国際金融都市OSAKA戦略
「経済の血液」とも言われる金融機能の強化を図り、ポストコロナに向けた大阪・関西経済の再生に向けた新たな成長の柱とするため、独自の個性・機能を持つ国際金融都市の形成をめざす。
取組期間
①短期(第一期活動期):2025年度(大阪・関西万博まで)
②中期(第二期活動期):2030年度(SDGs達成目標年度)
③長期:2050年度(カーボンニュートラル目標年度)
戦略目標
- 2025年度までに30社の金融系外国企業(フィンテック含む)・投資家等の誘致
- 2024年度までにユニコーン3社、スタートアップ300社創出
大阪府・市の「国際金融都市構想」の誘致企業(10社)
- フィンテック協会
- 大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)
- モルガン・スタンレーMUFG証券(事業継続計画BCP拠点)
- レイヤーエックス(フィンテック企業・請求書の処理や経費精算のソフト)
- スペーシアネットジャパン(日本に滞在するカンボジア人向けに本国への送金サービス)
- ベインキャピタルの日本法人(米投資ファンド)
- ソーシング・ブラザーズ株式会社
- 彰化商業銀行株式会社(台湾)
- トリニティ・テクノロジー株式会社(家族信託の組成コンサルティング)
- ザシードキャピタル株式会社(ベンチャーキャピタルファンド)
コメント
当ブログの考えでは、国際金融都市構想の計画を中止して「TSMC第三工場の誘致」「2030年、大阪のインバウンド消費額3兆円」を目指すべきだと思う。
そもそも、外資系金融機関を大阪に誘致してメリットがあるかどうか疑問がある。
誘致企業の数合わせのために税金を投入したり、インフレで日本人の生活が苦しくなっているのに「外資系金融機関」の税金を優遇してメリットがあるのか?
外資系金融機関は、大阪を発展させようとは1mmも思っていない。自分たちの利益があれば大阪に進出するが、税金優遇がなければ、すくに撤退する。
外資系金融機関というのはそういうもので、大阪府市の担当者は外資系金融機関の実態を知らなさすぎる。
国際金融都市構想を大幅に縮小する勇気を持つべきだ。
外資系金融機関にとって大阪進出は意味がない
外資系金融機関のシンガポール支店長の年収は10億円。
シンガポールの個人所得税は22%なので手取りは7億8000万円。
日本なら所得税45%と住民税10%の合計55%税金がかかり、手取りは4億5000万円。
手取り年収が3億円も減るので、日本に進出するわけがない。
また、シンガポールは株式の売買(キャピタルゲイン)も非課税だ。
税金を考えれば、大手外資系金融機関が日本に進出するメリットは何もない。
何度もいうが、大阪府の担当者は、国際金融について一般的な知識すらないし、海外の税制についても詳しくないと思う。
外資系金融機関の実態
2023年9月1日、セブン&アイ・ホールディングス(HD)は、「そごう・西武」を米投資会社「フォートレス・インベストメント・グループ」に2,200億円で売却した。
今後、ヨドバシHDが3,000億円で西武池袋本店の土地・建物などを買収する予定。
当ブログの理解では、外資系金融機関は2,200億円で「そごう・西武」を買収して、ヨドバシHDに3,000億円で「西武池袋本店の土地・建物などの不動産」を売却する。
単純に考えて外資系金融機関は800億円の利益を得る。
ヨドバシHDが欲しいのは「西武池袋本店の土地・建物など不動産」であって、「そごう・西武」の百貨店事業は欲しくない。
もし、ヨドバシHDが「そごう・西武」の百貨店事業も買収すると、その後、大幅なリストラを実行することになり、時間も手続きも膨大になり、企業イメージも悪化する。
それを避けるために、外資系金融機関を仲介させるのだと思う。
外資系金融機関は短期間で数百億円、数千億円の利益を追求する傾向にある。
外資系金融機関への補助金税制優遇
「国際金融都市OSAKA戦略」では、外資系金融機関を誘致するため「金融系外国企業等の拠点設立に向けた事前調査のためのオフィス賃料や、事業開始直後の必要な初期費用等の補助制度を創設」している。
さらに、税制優遇を国に働きかけるとしている。
外資系金融機関を大阪に誘致してメリットがあるのか?
外資系金融機関は「大阪を発展させるために、大阪に進出する」とは1ミリも思っていない。
外資系金融機関は、短期間で膨大な利益を得ることが目的だ。
そのために、有利な都市に進出し、メリットがなければ撤退する。
当ブログが思うに、大阪府・市がやっていることは「外資系金融機関を誘致すれば、国際都市になるだろう」という程度の「ふんわり」したイメージしかない。
そこには、戦略も戦術もなく、単に補助金を投入し税制優遇し「外資系金融機関」の誘致会社の数を積み上げる作業でしかない。
東大阪の町工場がターゲットになるかもしれない
「東大阪の町工場」と「外資系金融機関」は結びつかない。しかし、実際は中国資本が東大阪の町工場を買収している。
外資系金融機関が大阪に進出した場合、例えば、東大阪の町工場10社をまとめて100億円で買収して、中国企業に300億円で売却するような事態が発生するかもしれない。
大阪府市の担当者は、外資系金融機関の誘致をするよりも、まずは「東大阪の町工場」の実態を足で歩いて調査すべきではないか?