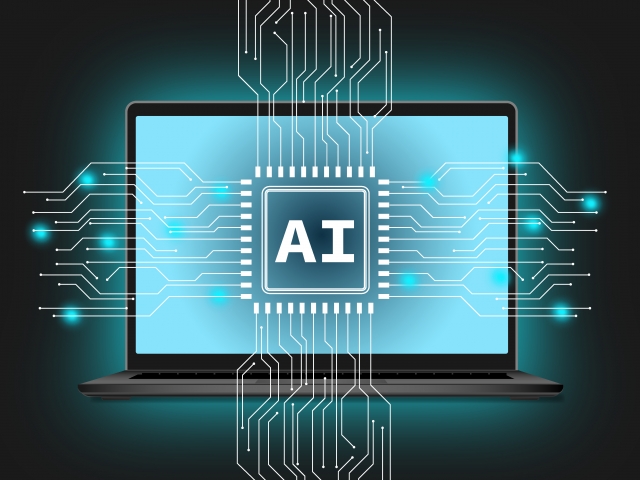2024年から始まった「新NISA」で投資を始める人が一気に増えました。でも実際には「何を買えばいいの?」「どんな運用をすればいいの?」と迷ってしまう方も多いと思います。
そんな中でおすすめなのが、誰でも取り組みやすいインデックスファンドを中心にしたシンプルな投資法です。本記事では、初心者でも安心して続けられる運用の考え方や、失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。
誰でもできる!新NISAの投資方針
インデックスファンドを中心に
投資のプロであるファンドマネージャーでさえ、長期的に見ると「市場全体の平均」(インデックスファンド)に勝てる人は1割もいません。
それなら、わざわざ難しい銘柄選びをしなくても、最初から「平均」を取るインデックスファンドに投資しておけば十分。時間をかければ着実に資産を増やせる方法です。
特に人気なのは以下のようなファンドです。
- S&P500インデックスファンド(アメリカの主要500社に投資)
- 全世界株式インデックスファンド(世界中の株式に分散投資できる)
どちらも長期的に右肩上がりの成長をしてきた実績があり、初心者でも安心して持ち続けられる商品です。ただし、過去データでは10年~20年に1回は基準価格が50%下落しています。
コアサテライト戦略
すべてをインデックスファンドにするのも安心ですが、投資を楽しむ気持ちも大事です。そこで役立つのが「コアサテライト戦略」です。
- コア(約8割) → インデックスファンドで着実に増やす
- サテライト(約2割) → 個別株やテーマ型ファンドでちょっとリスクを取る
こうすることで「安定」と「楽しみ」を両立できます。失敗しても大きな痛手にはならず、成功すればリターンを少し上乗せできます。
ギャンブル的投資をしない
「短期間で一気に増やす」投資はとても魅力的に見えます。
たとえば、1週間で100万円が120万円になったら嬉しいですよね。でも同じくらいの速さで、むしろそれ以上にお金が減るリスクもあります。
投資はマラソンのようなもの。コツコツ積み立てて、10年・20年かけて資産を大きくする方が結果的には確実です。焦らず、地道に続けることが一番の近道です。
こんなユーチューバーを信用してはいけない
個別株を薦めるユーチューバーは信用してはいけない。
前述のように、プロのファンドマネージャーの9割は、市場平均(インデックスファンド)の成績に勝てません。個人が投資するなら「インデックスファンド」しかありません。
配当・優待目的の株を薦めるユーチューバーは信用してはいけない。
配当や株主優待は一見すると魅力的に思えます。しかし、10年~20年先を見据えると、その特典が将来も続く保証はありません。実際にJALは経営破綻を経験しましたし、東京電力の株価もかつて5,000円から500円へと10分の1に下落しました。
さらに配当利回りは年3~4%程度にとどまります。一方でインデックスファンドには、長期的に年10%を超える利回りを示しているものも少なくありません。
株主優待も、たとえば50万円投資して年間3,000~5,000円の特典では、利回りにして1%にも満たないのが実情です。
つまり、配当や優待を目的とした投資は、長期的な資産形成の効率という面ではインデックス投資に劣る可能性が高いのです。
どんなインデックスファンドか?
株式投資についてしっかり勉強を重ねれば、最終的にはS&P500やオルカン(全世界株式インデックス)に行き着くはずです。
大切なのは、自分で調べて考え、この結論に納得してたどり着くことです。
なぜなら、人から『S&P500がいい』『オルカンが安心』と結果だけを聞いて投資しても、本質を理解していなければ相場が下がったときに不安になり、途中で投げ出してしまう可能性が高いからです。
インデックスファンドが半分になる覚悟をすべき
インデックスファンドは、10年~15年に1~2回、基準価格が40%~50%下落することがほぼ確実です。たとえば、2008年のリーマンショックではS&P500が57%も下落しました。しかし、その後5年で基準価格は回復し、その後の10年で10倍に成長しました。
投資資金が2,000万円の場合、半分の1,000万円に減少すると、多くの投資家は損切りしてしまうと言われています。
損切しなくても、基準価格が戻ったときに売却してしまい、利益を取り逃すことになる人も多いです。
こうした局面でも持ち続けるには、自分の投資に『自信』を持つことが不可欠です。そしてその自信は、人から聞いた情報では得られません。自分で調べ、考え、S&P500やオルカンへの投資が適切だと納得してたどり着くことが重要なのです。