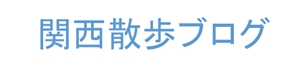グラングリーン大阪(JR大阪駅北側)
- 東京の都市圏人口は約3,400万人
- 大阪の都市圏人口は約1,200万人
- 東京は大阪の約3倍の都市規模
世界的に見れば、都市圏人口は東京が1位~5位、大阪が10位~20位と評価されることが多い。
関西圏の人口は約2,000万人だが、京都市や神戸市は独自の都市圏を形成している面もあるので、ここでは大阪都市圏を1,200万人とする。

JPタワー大阪(地上39階・高さ188m・延床面積23万㎡・2024年3月竣工)
結論から言うと、2024年2月現在で、新宿の規模を100とすると大阪梅田の規模は90くらいだと思う。
しかし、2024年9月6日、JR大阪駅の北側に「グラングリーン大阪」の北街区や公園の一部が街びらきし、2025年春には南街区のビルやホテルが開業する。
新宿と言っても、西新宿~東新宿~歌舞伎町と面積が広い。
同じ条件で比較するために、大阪梅田~中之島まで範囲を広げると、大阪梅田~中之島が新宿の規模を上回る可能性もある。
2031年春、大阪では鉄道路線「なにわ筋線」が開業し、大阪梅田~中之島が1駅で結ばれ一体化する。
さらに、中之島5丁目開発予定されており、既存の施設と合わせると延床面積100万㎡という大規模なものになる。

大阪梅田ツインタワーズ・ノース(41階・高さ187m・延床面積約25万㎡・2010年竣工)
高さ100m以上の超高層ビルの棟数は、東京約600棟、大阪200棟で、やはり東京は大阪の3倍の規模と言える。

2024年2月(中央南口)
東京全体では大阪全体の3倍の規模だが、主要駅から半径800mのエリアで考えるとそこまでの差はない。
| 項目 | 大阪梅田駅 | 新宿駅 | 東京駅 |
| オフィス従業員数 | 50% | 60% | 100% |
| 小売従業員数 | 90% | 100% | 50% |
| 飲食店従業員数 | 90% | 100% | 60% |
| 飲食店店舗数 | 100% | 90% | 40% |
| 遊興・サービス従業員数 | 90% | 100% | 50% |
| 100室以上のホテル客室数 | 100% | 90% | 40% |
| 映画館座席数 | 90% | 100% | 10% |
| 劇場座席数 | 60% | 30% | 100% |
| イベントホール(床面積100㎡以上) | 80% | 60% | 100% |
| 会議室(床面積100㎡未満) | 90% | 40% | 100% |

大阪梅田ツインタワーズ・サウス(38階・高さ189m・延床面積約26万㎡・2022年竣工)
東京駅と梅田を比較すると、ビジネス街は東京駅の方が大きいが、商業街としては梅田の方が大きい。
新宿駅は「商業エリア」「ビジネスエリア」とも梅田よりも1割大きい。
| エリア | ビジネス(オフィス) | 商業 | 総合順位 |
| 東京駅 | 1位 | 3位 | 3位 |
| 新宿駅 | 2位 | 1位 | 1位 |
| 大阪梅田駅 | 3位 | 2位 | 2位 |
大阪梅田駅は、ビジネス、商業とも新宿の9割の規模で、総合的に考えると日本第2位のエリアと言えるかもしれない。

JR大阪駅北側
東京駅の八重洲口側に「日本橋三越本店」や「日本橋高島屋」があるが、東京駅から徒歩15分くらいで回遊性はない。したがって、「東京駅の丸の内」と「日本橋」は「一つのエリア」とするには無理がある。
また、銀座はショッピングやレストランのエリアではあるが、ビジネス街ではない。
渋谷駅周辺にも4棟の超高層ビルが完成したが、ビジネス街としては大阪梅田の方が大きい。
東京23区全体を俯瞰して見ると、大阪市の3倍くらいの規模だ。
しかし、半径800mのエリアとしてみた場合、大阪梅田エリアほどビジネス・ショッピング・レストランなどがバランスよく集積しているエリアは東京でも新宿以外にない。
その新宿も東西にエリアが分かれているので、大阪梅田ほど集積していない。

「うめきた2期」三菱地所案(出典 UR都市機構)
JR大阪駅北側は、超高層ビル街になりつつあるがJR大阪駅の周囲を見渡すと再開発が完了していない物件がある。
これらの再開発物件は2025年春までに、ほぼ竣工する予定で、そうなれば大阪梅田が新宿を追い抜く可能性がある。
つまり、2025年春に大阪梅田が日本一の「商業・ビジネス」の集積地となるかもしれない。

グランフロント大阪(2013年開業)

2024年6月(グラングリーン大阪)

うめきた南街区には、ヒルトンの最上級ホテル「ウォルドーフ・アストリア大阪(252室)」が2025年開業予定。

完成予想図(出典 JR西日本)
2025年までに「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」「JPタワー大阪」「グラングリーン大阪」が完成すれば、誰が見ても「大阪梅田」が日本最大級の「商業・ビジネス」の集積地と実感できるだろう。
東京の長時間通勤、割高な不動産価格、過密など世界基準から見ると限界を超えている。
東京で快適に暮らすなら世帯年収3,000万円くらい必要だが、大阪なら世帯年収1,000万円で快適に暮らせる。
東京生活をやめて大阪で生活する人が増加するかもしれない。
現在でも20代女性は大阪で就職する人が増加している。この動きが2025年頃から男性にも広がる可能性は十分にある。
時代の流れや勢いは「大阪」にある。
「時代の転換期の瞬間」って分かり難いもので、後から「あの時が転換期だったなあ」と思うものだ。
その転換期が2025年頃かもしれない。
すでに、福岡、三重、静岡、沖縄などのホテルチェーンが大阪に進出している。
「東京は1億2000万人の日本の中心」だが、「大阪は45億人のアジアに近い」。
45億人のアジアから大阪に観光客やビジネス客を呼び込み、アジアの成長力を大阪に取り込むことに成功すれば、大阪は再び日本一の経済都市になることも不可能ではない。
「梅田(大阪)」と「新宿(東京)」のどちらの人出が多いか?
人によって答えが違うと思うが、産経新聞に「スマホの位置情報」を解析した「1日当たりの滞在人口」が掲載されている。
| 日時 | 梅田駅(大阪) | 新宿駅(東京) | すすきの駅(札幌) | 栄駅(名古屋) | 天神駅(福岡) |
| 2020年1月25日(土) | 194,000人 | 167,000 | 99,000人 | 73,000人 | 91,000人 |
出典 産経新聞
2020年1月25日(土)の普段の土曜日の人出は、「梅田(19.4万人)」・「新宿(16.7万人)」と梅田の方が多かった。
「梅田」が「新宿」と並ぶ日本最大級の商業地区であることは間違いない。
2024年~2028年にかけ「うめきた2期」(大阪駅北)が開業すると「大阪・梅田」が「日本1位の商業地区」になる可能性もある。
日本1位と言うことは、世界1位ということだ

「うめきた2期」三菱地所案(出典 UR都市機構)
意味のない乗降客数
| 順位 | 駅名 |
| 1位 | 新宿駅(JR東 乗車79万人)+地下鉄+私鉄 |
| 2位 | 渋谷駅(JR東 乗車37万人)+地下鉄+私鉄 |
| 3位 | 池袋駅(JR東 乗車57万人)+地下鉄+私鉄 |
| 4位 | 大阪・梅田駅(JR西 乗車43万人)+地下鉄+私鉄 |
| 5位 | 横浜駅(JR東 乗車42万人)+地下鉄+私鉄 |
新宿駅は日本一の乗降客数で1日300万人以上と言われるが、この数字には私鉄からJRへの乗換客も算入されている。
つまり、単に新宿駅で乗換する人が多いというだけでしかない。
この数字を根拠に「新宿が日本一の商業地」と東京マスコミは放送しているが、正確な分析ではない。
今後スマホの位置情報を基にした正確なデータ分析が一般化すれば、大阪(梅田)に出店する企業が多くなる。

JR大阪駅北側「リンクス梅田」と「グランフロント大阪」
JR西日本乗車人数(2018年1日平均)
| 順位 | 駅記名 | 乗車人数 |
| 1位 | 大阪駅 | 433,637人 |
| 2位 | 京都駅 | 200,426人 |
| 3位 | 天王寺駅 | 147,871人 |
| 4位 | 京橋駅 | 135,294人 |
| 5位 | 三ノ宮駅 | 124,917人 |
| 6位 | 鶴橋駅 | 100,067人 |
| 7位 | 広島駅 | 77,169人 |
| 8位 | 神戸駅 | 70,925人 |
| 9位 | 岡山駅 | 69,571人 |
| 10位 | 新今宮駅 | 66,083人 |
JR西日本管内でも、5位「三ノ宮(12万人)」、6位「鶴橋駅(10万人)」と乗車人数の差は少ないが、これは「鶴橋駅」で近鉄から「JR大阪環状線」に乗換える客が多いという数字でしかない。
JR大阪駅に新幹線乗り入れすべき
旧大阪中央郵便局建替(2024年開業)完成予想図(出典 JR西日本)
JR東海の資料によると「東京駅(新幹線)」乗車人数104,451人、「新大阪駅(新幹線)」84,467人で、新大阪駅は東京駅の8割程度と新幹線需要は大きい。
東海道新幹線は1日370本が運行されているが、新大阪始発・着便(のぞみ200番台・300番台・400番台など)は1日120本~150本で、朝夕は1時間当たり3本~4本の新大阪駅始発便が運行されている。
したがって、新大阪駅~大阪駅(約3.8km)に新幹線線路を敷設してもいいくらいの需要がある。
JR東海とJR西日本との境界線の問題もあり簡単ではないが、北陸新幹線はJR大阪駅まで延伸すべきだ。
将来的にJR東海を東西に分割することになれば、JR大阪駅から「北陸新幹線線路」を使って新大阪駅まで行き、そこから東海道新幹線に乗り入れすればいい。