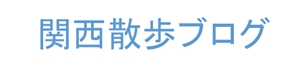日本全国にはいくつかの「地域連携軸構想」があり、西日本では「西瀬戸経済圏構想」「西日本中央連携軸構想」などがある。
この「地域連携軸構想」は東京一極集中ではなく「分散型国土」を形成することにより、国土資源の有効活用を図り多様で豊かな国土を形成するとともに、過密、過疎を解消しすることを目的としている。
主な西日本の地域連携軸構想
| 地域連携軸構想 | 人口 | 面積 |
| 西瀬戸経済圏構想 | 970万人 | 3.3万㎢ |
| 西日本中央連携軸構想 | 600万人 | 4.6万㎢ |
| 中四国地域連携軸構想 | 600万人 | 2.8万㎢ |
| 東九州軸構想 | 430万人 | 1.4万㎢ |
| 九州中央軸構想 | 950万人 | 2.4万㎢ |
| 九州北部地域連携軸構想 | 740万人 | 1.1万㎢ |
| 南九州広域交流圏構想 | 480万人 | 2.4万㎢ |
出典 国土交通省
大阪との関係性
大阪文化の一つ「出汁(だし)」は北海道の昆布と鹿児島のかつお節が大阪で出会ってできたものだ。
江戸時代から大阪は日本の物流の中心であり、そこから大阪文化が育まれた。
また、人材と言う点でも、阪急の創業者「小林一三氏」は山梨県出身、「関一大阪市長」は静岡県出身、大阪証券取引所の前身「大阪株式取引所」を設立した「五代友厚氏」は鹿児島出身と全国から優秀な人材が大阪に集まって大阪を発展させた。
1990年代のバブル崩壊前までは、大阪は九州・中国・四国の圧倒的中心都市であったが、2000年4月以降の航空運賃の自由化により、羽田=福岡路線などの運賃が値下がり、飛行機を利用し易くなった。
この結果、九州・中国・四国から大阪を飛び越え、飛行機で東京と直接往来することが多くなり、大阪の地盤沈下につながった。
しかし、2011年3月、九州新幹線が全線開通し、新大阪駅から直通で行けるようになり、交流人口が3割増加した地域もある。
2022年9月には西九州新幹線(長崎=武雄温泉)が開業するなど、再び、大阪と九州各地との結びつきが強くなってきている。
アジア・ゲートウエイ構想とのリンク
アジア・ゲートウエイ構想とは、アジアの成長と活力を日本に取り込もうという趣旨で2007年に第1次安倍政権が掲げた構想で、九州各県もアジア・ゲートウエイを意識し港湾や空港などのインフラを整備している。
大阪もアジアからのインバウンド需要を取り込み経済成長しており、九州各県と協力することができると思う。
「環瀬戸内海地域交流促進協議会」を拡大できないか?
主として中国・四国地方の交流人口拡大を目的に「本四架橋」の所在県をメンバーとした「環瀬戸内海地域交流促進協議会」が発足している。
現在のメンバーは、広島県、岡山県、兵庫県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県と中国整備局などが参加している。
この組織を「環瀬戸内海経済圏」に格上げし、関西各県と九州各県も参加して「西日本の巨大地域経済圏」を形成し、一体的に「アジアゲートウエイ」を目指すべきではないか?
一都市だけで「アジアゲートウエイ」となるのではなく、「西日本」が一体的に「面」として日本の「アジアゲートウエイ」になるべきだと思う。
(仮称)拡大環瀬戸内海地域交流促進協議会
| 府県名 | 人口 |
| 広島県 | 280万人 |
| 岡山県 | 190万人 |
| 兵庫県 | 550万人 |
| 大阪府 | 880万人 |
| 京都府 | 260万人 |
| 奈良県 | 136万人 |
| 和歌山県 | 96万人 |
| 徳島県 | 75万人 |
| 香川県 | 97万人 |
| 愛媛県 | 138万人 |
| 福岡県 | 510万人 |
| 大分県 | 116万人 |
| 山口県 | 140万人 |
| 合計 | 3468万人 |
首都圏との違い
首都圏は東京を中心に同心円状に広がっており、中心都市である東京にすべてが集中する構造になっている。
一方、「環瀬戸内海経済圏」は大阪が中心ではなく「瀬戸内海」が中心であり、各地域がリング状につながっており、東京圏のように東京に集中する構造ではない。
まさに、東京一極集中を是正する「環状経済圏」と言えるのではないか?