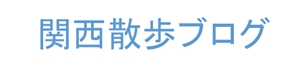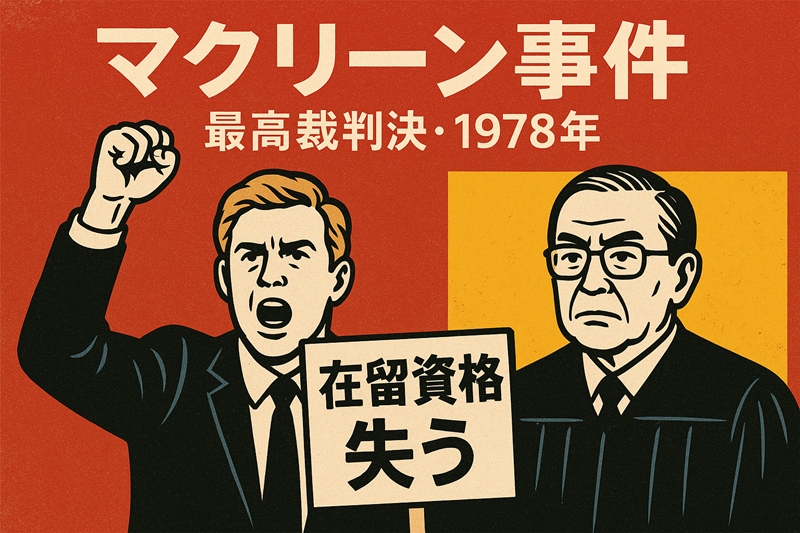
日本に住む外国人が、政治的な活動を行った場合にどこまで自由が認められるのか。
この問いは、実は半世紀以上前の有名な裁判─「マクリーン事件(最高裁判決・1978年)」にまでさかのぼります。
この事件は、外国人の政治的自由と在留資格の関係をめぐる日本の憲法判例の中でも、最も重要なものの一つです。
この判決により、次のような原則が確立しました。
- 日本に滞在する外国人も、人権の主体ではある(=基本的人権の享有主体)。
- ただし、政治的活動の自由は制限を受けることがある。
- 特に在留資格の更新・許可は「国家の裁量」によって決定される。
つまり、外国人の政治活動が「日本の外交や治安に悪影響を与える」と判断されれば、
在留資格の更新拒否や退去強制の対象になりうるということです。
マクリーン氏は、アメリカ合衆国出身の英語教師で、1960年代に日本に滞在していました。
彼は日本の大学などで英語を教える傍ら、ベトナム戦争に反対する平和運動に参加していました。
当時、日本では全国的に「反戦デモ」や「米軍基地反対運動」が盛んに行われており、マクリーン氏もこれに参加したのです。
しかし、その後、在留資格(ビザ)の更新申請をしたところ、法務大臣がこれを不許可(更新拒否)としました。
その理由は、「日本国内における政治的活動が在留資格の趣旨にそぐわない」と判断されたためです。
1978年(昭和53年)に最高裁が出した最終判断は、現在でも重要な基準とされています。
最高裁は、次のように述べました。
- 外国人にも「人としての基本的人権」は尊重される。
- しかし、それは日本の法秩序の下で認められる範囲に限られる。
つまり、外国人にも表現の自由や思想の自由は原則として認められるが、その行使が「日本の主権や法秩序を脅かすおそれがある」と判断される場合には、制限されることがあるという立場を示したのです。
そして最高裁は、法務大臣の在留更新拒否を「裁量の範囲内」と認め、マクリーン氏の訴えを棄却しました。
マクリーン事件から半世紀が経った今、日本に住む外国人の数は約320万人に達しています。
SNSを通じて政治的意見を表明する外国人も少なくありません。
しかし、選挙運動への参加やデモの主催といった政治的活動には、制限があります。
入管法(出入国管理及び難民認定法)上も、外国人が政治的に「内政に介入する」ような行為は、
在留資格に悪影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などで滞在している外国人が、
政治団体の活動やデモを主導した場合、「在留目的に反する活動」とみなされ、更新拒否の理由となることがあります。
参考文献
- 最高裁判所昭和53年10月4日判決(マクリーン事件)
- 出入国管理及び難民認定法
- 芦部信喜『憲法(第7版)』岩波書店