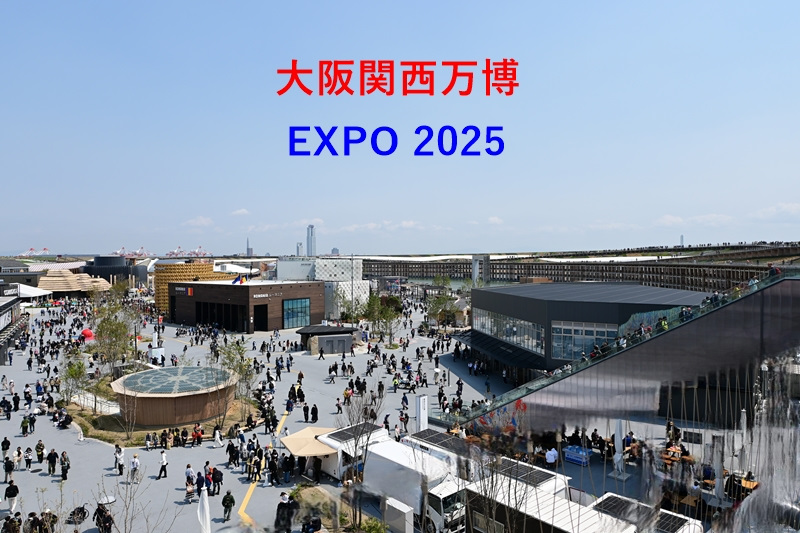「PIVOTのYouTube動画」では、2025年大阪・関西万博の開催を前に、建築家・藤本壮介氏と社会学者・宮田裕章氏が対談した「万博とは何だったのか?」が紹介されています。この動画は単なるイベント紹介にとどまらず、建築や社会、未来に関する深い問いを投げかけています。
本稿では、両者の議論から浮かび上がった建築デザインの思想や社会・文化的意義、批評的視点を整理しつつ、現代の万博が持つ意味を改めて考えてみたいと思います。
PIVOTの動画が非常に印象的だったため、まず私が2025年大阪・関西万博について考えたことをまとめ、次にAIが作成した「PIVOTの動画」の要約を掲載します。
1970年万博──明確なコンセプトが時代を牽引した
1970年の大阪万博は、日本の高度経済成長期に開催されました。テーマは「人類の進歩と調和」。当時の日本は、経済成長の右肩上がりが当たり前とされ、未来に対して明確なビジョンを国民全体が共有していました。
そのため、万博のコンセプトは極めて明快であり、技術の進歩や豊かさの象徴として国民の期待を一身に集めることができました。
明確なコンセプトが、社会のエネルギーを束ね、都市や経済を動かす力を持つことを示した典型例でした。
しかし、21世紀になると状況は大きく変わります。1990年代のバブル崩壊以降、日本は「失われた30年」と呼ばれる長期停滞期を迎えました。社会構造も多様化し、格差が広がりました。
- 氷河期世代:時給800円のアルバイトや派遣生活に苦しむ
- IT・投資富裕層:一部の人々は投資やテクノロジーで成功
- 地域格差・首都圏一極集中・世代格差の拡大
社会は一枚岩ではなくなり、単一のコンセプトで全員に響かせることは困難になりました。こうした分断社会では、「明確なターゲット(多くの場合は富裕層)」に焦点を当てた従来型のビジネスモデルや都市づくりは時代遅れになりつつあります。
2025年万博─多様性とリアルな体験
2025年大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。1970年万博のように「未来像を明確に提示する」ものではなく、やや理解しづらい側面があります。これは、多様性の時代に突入したことが背景にあります。
この特徴は、開幕前のSNS上の批判からも見えてきます。多くのアカウントが事前に懐疑的な意見を投稿していましたが、実際に訪れた人の多くは楽しみ、何度も足を運んでいます。つまり、「行かないとわからないリアル体験」が評価を一変させたのです。
これは、明確なターゲットや単一のコンセプトに依存していた20世紀型モデルとは正反対です。多様性をリアルに体験することが、新しい時代のコンセプトになっていると言えるでしょう。
大屋根リング─物理的空間に宿る新しい社会の象徴
2025年万博のレガシーとして注目されるのが、会場を囲む巨大な「大屋根リング」です。これは単なる建築物ではなく、社会や街づくりのあり方を象徴する存在です。
- すべての人を受け入れる空間
- 多様性を包み込みつつ、ゆるやかに統一性を持たせる
- 特定の価値観や層に限定されない開かれた社会の象徴
この「ゆるやかな統一性」は、多様な人々や価値観が共存する21世紀社会における、新しい街づくりや都市設計のヒントとも言えます。
明確なコンセプトから「開かれた問い」へ
1970年は「進歩と調和」という明確な答えを提示しました。
2025年は「多様性とリアル体験」という開かれた問いを投げかけます。
- 明確なコンセプト:時代を一方向に導く装置
- 多様性のコンセプト:時代を映し出す鏡
開かれた問いとしてのコンセプトは、参加者自身が体験を通して感じ、解釈し、未来を考えることを促します。これは、単に建築物や展示を見るだけではなく、実際に現場で体験することの意味を強く示しています。
まとめ─2025年万博の示す未来
2025年大阪・関西万博は、もはや「未来はこうなる」を示すイベントではありません。
「あなたは何を感じ、どんな未来を選ぶか」を問いかける体験型の実験場です。
そしてその象徴が、大屋根リングです。
- 物理的な空間として人々をつなぐだけでなく
- 多様性の時代におけるゆるやかな統一性の象徴として存在する
この万博のレガシーは、これからの街づくりや社会構築のヒントを示していると言えるでしょう。
単一のコンセプトに縛られない、多様性を包み込む街づくり。それこそが、21世紀の日本社会に求められる、新しいビジョンなのです。
そういう観点から見ると、2025年大阪・関西万博は、従来の社会のあり方やビジネス、都市づくりの方向性とは異なる、新しい方向性を示す画期的なイベントだと言えます。
ただし、この意義が一般社会に広く認知されるには、数年から十年以上かかる可能性があります。また、万博を直接体験していない人は、表面的には理解できても、心の底からその価値を感じることは難しいかもしれません。
そう考えると、万博を実際に体験した人々は、体験していない人々とは違った角度から、世界の景色や価値を感じ取ることができるのかもしれません。
ぜひ、この1970年以来、55年ぶりの貴重な体験を、それぞれの心にそっと刻み、これからの人生のささやかな「道しるべ」や、静かに灯る「心の炎」にして欲しいと思います。
藤本壮介が設計を担当する大阪・関西万博の象徴的建造物が「大屋根リング」である。
直径約2キロにも及ぶ巨大なリングが会場を囲み、その中心には森が配置される。この構想は、単なるランドマークとしてではなく、“小さな地球”を象徴するものとして語られている。
藤本は建築を「完成されたオブジェ」ではなく、人と自然が関わり続けることで意味が更新される“場”として捉える。
中心に森を据えることで、人間中心の価値観を相対化し、自然を主役に据える空間を実現しようとしているのだ。
屋根リングは森を包み込みながらも内と外の境界を曖昧にし、人々が自由に出入りできる設計となっている。
この曖昧さは、都市と自然、人工と野生、公共と私的領域といった対立的概念を共存させる装置として機能する。
藤本が重視するのは「未完成性」である。
建築は完成と同時に終わるものではなく、利用者が自由に解釈し、使い方を変え、記憶を重ねることで進化していく。
万博の会場は、設計者の意図を押し付ける空間ではなく、人々が意味を発見し続ける「つくり続けられる建築」として計画されている。
宮田裕章が提示したキーワードが「共鳴(レゾナンス)」である。
共鳴とは単なる調和や一致ではなく、摩擦やズレを含みながら互いに響き合うプロセスだという。
万博という場は、異なる文化や価値観が交わる「世界の縮図」であり、共鳴の実験場でもある。
19世紀の万博は国家が技術力を競うショーケースだったが、21世紀の万博に求められるのは“違いを尊重した共存”である。
宮田は、共鳴を通じて「違いを前提にしたつながり」を生み出すことが、未来社会に不可欠だと語る。
これは均質化された共通性を目指すのではなく、異なる価値がぶつかり合いながら新しい意味を創発するプロセスだ。
対談では植物神経学や非人間知性など、建築以外の専門家も議論に参加した。
植物の知性や非人間的存在との共存は、人間中心主義を揺さぶるテーマであり、
万博を「人類の展示」から「地球規模の生態系との共生の実験場」へと位置づけ直す視点が示された。
藤本が中央に森を据えた設計は、まさにこの思想を体現している。
また、万博が終わった後も、会場が持つ記憶や体験は都市の文化資産として残る可能性がある。
藤本は建築を「文化の触媒」と捉え、単なる物理的遺構ではなく、人々の記憶や感情を媒介する装置として機能させたいと語った。
これは万博を「一過性のイベント」から「未来への種まき」へと変える試みでもある。
とはいえ、万博には矛盾もある。
地球との共生を掲げながら、実際には膨大な資材やエネルギーを消費する巨大イベントであることは否めない。
建設や運営に伴う環境負荷、莫大な費用、開催後の施設活用など、現実的な課題は多い。
藤本と宮田が強調する「共鳴」は魅力的な概念だが、摩擦や対立をどう具体的に調整するかは未解決だ。
異なる価値観を尊重する設計が、政治的・経済的制約の中でどこまで実装できるのか。
また、万博が終わった後にその理念が都市計画や社会制度へ持続的なインパクトを与えられるかは、今後の検証が必要だ。
しかし、こうした矛盾や限界を抱えながらも、万博が新たな社会モデルを試みる場であることに意味がある。
藤本が語る「未完成性」や宮田が提唱する「共鳴」は、まさに解決しきれない課題を引き受ける勇気を示している。
藤本壮介と宮田裕章の対談は、建築やイベントを超えて、未来社会への哲学的な問いを投げかける。
異なるものがぶつかり合い、摩擦を伴いながらも響き合うことで、新しい価値が生まれる。
万博はその実験場であり、完成された答えではなく、問いを提示する場として存在する。
2025年大阪・関西万博がどのような評価を受けるにせよ、
この対談が示した「共鳴」の思想は、私たちがこれから直面する多様性の時代において重要なヒントを与えてくれる。
違いを恐れず、ズレや摩擦を受け入れながら共に生きる社会──。
その可能性を、万博という“未完成の場”から感じ取ることが、私たちに求められている。
藤本壮介が目指すのは、利用者が意味を発見し続ける“未完成の建築”。
宮田裕章が掲げるのは、摩擦を抱えたまま響き合う“共鳴”の社会。
万博は、巨大イベントでありながら、未来社会に必要な問いを投げかけるプラットフォームとなり得る。
その答えは、完成した建物の中ではなく、会場を訪れる一人ひとりの経験と記憶の中に芽生えていくのだ。